コミュニケーターの制度を
最近受けた相談で、大事だなと思ったことがありました。
弁護士に相談している方が、「弁護士の言っていることがわかりづらい」とか、「弁護士にわからないことを質問しづらい」「この解釈で合っているか心配」といって、私に聞いてくることがありました。
事柄によっては一応専門家の方に聞いた意見を紹介したりするなどして対応しつつ、最終的にはやはり、「勇気を持って、担当の弁護士さんにわからないことや心配なことは聞いてみたほうがいいよ」とアドバイスし、精神的バックアップをしました。結果、相談者の方は担当の弁護士さんに聞けたということで安心しました。
この経験から、やはり、こういうニーズはたくさんあるのだろうなと思いました。
もしかすると、多くの人が、よくわからないまま、モヤモヤしながら、専門的な会話のやりとりを正確に完璧に理解することを諦めたり、精神的に不安になったりしているかもしれないと思いました。
この問題についてヒントになる解決方法としては、以下の2つが思い浮かびます。
一つは、北海道大学が2005年からやっているCoSTEPという、科学技術コミュニケーターを養成し、専門的知識・情報について一般市民の理解を助けるコミュニケーションの手法やあり方を充実させ多様化するような試み・研究といいましょうか。
https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/qualifications
上記は科学技術に関してですが、セックスワーカーの法的支援版においては、ニカラグアのセックスワーカーのパラリーガル認定がいい例でしょう。
https://www.ibtimes.com/nicaragua-rolls-out-program-train-sex-workers-conflict-mediators-1962831
ニカラグアだけでなく中南米の数カ国では、このような一般市民がトラブルの仲介に入って司法仲介者をする司法制度が一般化しているそう。しかし、セックスワーカーをパラリーガルとして訓練して認定したのはニカラグアが世界初だそうです。
記事によると、ニカラグアはセックスワーカーのシチズンシップが他の分野においても進んでいるようです。「最高選挙管理委員会は、 2016年大統領選挙に向けたボランティア選挙アシスタントとして、セックスワーカーに研修を受けるよう公に要請した」とあります。
いずれも「組織化」が鍵のようです。
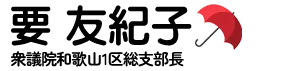

コメント