党議拘束を外せる法案というのはどういう法案なのか?
今週は、政治家に向いている人はどんな人かということや、役員幹部になる人はどういう人であるべきかみたいな話を聞く機会が2箇所であったのが印象に残っています。いずれも政治の世界に長らく身を置いてきた方々からのご意見を拝聴しました。
その人が何に向いてるか向いてないかというのは客観的なものだと思います。何でもやりたければやればいいんじゃないかと思う自分はやはりあほなのかなと思ってしまいました。
まだまだ政治の勉強が足りない私が今週読んでいる本についてご紹介します。

「女性議員は『変な女』なのか」(野田聖子・辻元清美の共著、小学館新書、2025年)を半分くらいまで読んだところです。そこで、勉強になるなあと思った部分を書いておきます。
「夫婦別姓に関しては法務省の法制審答申が最初に出たのは1996年で、私が当選した年なの。だから29年前に出て、そこから民法改正案は参議院で十五回、衆議院で九回出している」そうです(辻元、p.41)。
この選択的夫婦別姓に関して辻元さん、野田さんのお二人は、党議拘束を外してやるべきだと主張されています。
その中で、1997年に制定された臓器移植法のときは、各党党議拘束を外したエピソードが紹介されていました。
臓器移植法案の時の「脳死は人の死か」論争は私も当時新聞記事を読んだり、梅原猛の本を読んだりしたのでよく覚えています。
この法律は、脳死状態の人、つまり脳幹という部位を含む全ての脳の機能が失われた状態の人は死んでいると判定され、臓器移植できるようになった法律です。医学的な知識だけでなく、人間の死の線引きを巡る哲学的な議論や、いわゆる”植物状態”はじゃあどうなるのかなど、障害者団体からの反発も大きい法律でした。この法律のときは党議拘束がなかったそうです。
このときの党議拘束を外した背景や、その他の問題で党議拘束を外す法案と、外さない法案の違いがよくわからないので、今後調べてみたいと思いました。
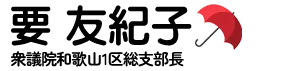

コメント